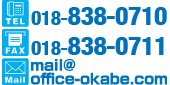「建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされています。
この建設業を行うにあたり、国土交通大臣や都道府県知事から受ける許可の事を「建設業許可」と呼びます。
どういった際に建設業許可が必要となるか?
「建設業」とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業の事をいいます。
つぎに「建設工事」とは、土木建築に関する工事とされていて、建設業許可の区分と業種に該当する28業種(※)の事をいいます。
※28行拾に関しては下記「許可の業種とは?」をご覧下さい。
最後に「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、その相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束したものです。
つまり簡単に言いますと建設業許可の区分と業種に該当する工事を行い、お金を得る行為を行っている事業者は、原則的に建設業許可が必要になるという訳です。
軽微な工事のみを行っている場合は、例外として建設業許可が必要ではないとされています。
では、建設業許可が必要ない軽微な工事とはどのようなものか?という定義ですが、以下のものを軽微な工事と呼んでいます。
| 建築一式工事以外 | 1件の請負金額が500万円未満 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円未満。 または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
つまり上記に当てはまる建設工事のみを行う場合は、許可は必要がない事になります。
※よく勘違いされる方がいらしゃるのですが、「元請」の建設工事を請け負う場合しか許可をとらなくてもい
いと思われている方が多いようです。
しかし残念ながら、「下請」業者も許可は必要なのでご注意ください。
建設業許可では、許可を受ける行政庁(誰の許可を受けるか?)と下請けに出す工事の規模によって区分されています。ですから、取得する必要がある区分を見極め建設業許可の申請を行う事となります。あなたの場合はどの区分に該当するか、一度考えてみてください。
区分1.知事許可か大臣許可か?
1つめの区分方法は許可を受ける行政庁(誰の許可を受けるか?)です。
これは大きく分けて都道府県知事の許可か?もしくは国土交通大臣の許可か?です。
どちらの許可が必要か?の判断方法ですが営業所の所在地によって区分されています。
営業所とは常時建設工事に関して契約の見積もり、入札、締結等を行う事務所のことです。(建設業の営業を行う事務所)
どういった際に建設業許可が必要となるか?
2つめの区分方法は工事を下請けに出す場合の下請け代金の額によって一般許可と特定許可に区分されています。
どちらの許可が必要か?の判断方法ですが発注者(官・民問わず)から直接工事を受注し、下請けに出す工事の総額が一定額以上になるか?によって区分されています。
その一定の額というのは以下の額(1件の請負工事につきの金額)とされています。
| 建築工事業以外 | 下請け金額の総計が3,000万円以上 |
|---|---|
| 建築工事業 | 下請け金額の総計が4,500万円以上 |
※この2つの区分方法の関係ですが、それぞれ完全に独立しています。つまり独立した区分を組み合わせた許可区分が存在するため、4つの区分に分かれている事になります。言葉では説明が難しいので、4つの区分を表にしておきます。
| 区分方法 | 一 般 | 特 定 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 知事許可・一般 | 知事許可・特定 |
| 大臣許可 | 大臣許可・一般 | 大臣許可・特定 |
許可の業種とは?
前述したとおり「建設工事」は28の業種に分類されています。
そして建設業許可は28の業種に対応した建設工事の種類ごとに許可の取得をする事とされています。
ですから、例え建設業許可を取得した業者であっても、許可を受けた建設工事の業種が「建築工事業」であれば、「ほ装工事」などの建築工事以外は軽微な工事しか行えない事となります。許可取得の際には、どの業種の許可が必要であるか?は良く考えて決定してください。
| 区分方法 | 一 般 | 特 定 | 特 定 |
|---|---|---|---|
| 土木工事業 | 土木一式工事 | 板金工事業 | 板金工事業 |
| 建築工事業 | 建築一式工事 | ガラス工事業 | ガラス工事 |
| 大工工事業 | 大工工事 | 防水工事業 | 防水工事 |
| とび・土工工事業 | とび・土工・コンクリート工事 | 内装仕上工事業 | 内装仕上工事 |
| 石工事業 | 石工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具設置工事 |
| 屋根工事業 | 屋根工事 | 熱絶縁工事業 | 熱絶縁工事 |
| 電気工事業 | 電気工事 | 電気通信工事業 | 電気通信工事 |
| 管工事業 | 管工事 | 造園工事業 | 造園工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル・れんが・ブロック工事 | さく井工事業 | さく井工事 |
| 鋼構造物工事業 | 鋼構造物工事 | 建具工事業 | 建具工事 |
| 鉄筋工事業 | 鉄筋工事 | 水道施設工事業 | 水道施設工事 |
| ほ装工事業 | ほ装工事 | 消防施設工事業 | 消防施設工事 |
| しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事 | 清掃施設工事業 | 清掃施設工事 |
つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。
建設業許可は誰でも取れるものではなく、許可を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たしていない場合申請が拒否されますので、その場合は要件を満たすよう(要件を確認できる書類を残すよう)に事前に行動するといった計画的行動が必要な場合もあります。
数年後の取得を目指す方も許可申請には色々と添付書類が必要ですので、早い目に当事務所までご相談ください。
要件1.経営業務管理責任者がいること
許可を受けようとする者が、法人の場合はその常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当していなければなりません。(ただし実際には3番目の要件は認められるケースは少なくなっております)
- 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業(の業種)以外の建設業(の業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること
※上記のいずれかに該当する方を事業経営に参画させると要件を満たすこととなります。
もしこれらの人物がいない場合には、該当者を役員に迎え入れる等の対応が必要になります。
要件2.専任技術者が各営業所にいること
許可を受けて建設業を行おうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する事務所に専任する技術者を常勤で置くことが必要となります。一定の資格・実務経験を有するとは、具体的には次のいずれかに該当する者をいいます。(一般許可と特定許可では一定の資格・実務経験の要件が異なります)
1)一般許可の場合
- 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、国土交通省令で定める学科(建築工事業の場合の建築科など)を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後、5年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、国土交通省令で定める学科(建築工事業の場合の建築工学科など)を修めて大学を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、10年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者(建設業法に規定する技術検定の合格者【二級土木施工管理技士など】等が該当します)
2)特定許可の場合
- 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者(一級土木施工管理技士など原則として一級試験合格者のことです)
- 一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者(一般建設業の専任技術者の要件を満たした人物が特別な経験をした場合です)
※ただし、指定7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)で専任技術者となる方は、この要件では認められません。 - 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者(国土交通大臣が特別に認めた者です)
※上記のいずれかに該当する方を事業経営に参画させたり、常勤の従業員として雇用すると要件を満たすこととなります。もしこれらの人物がいない場合には、該当者を雇用する等の対応が必要になります。
要件3.請負契約について誠実性があること
許可を受けようとする事業者が、法人の場合はすべての役員及び支店・営業所の所長や支配人が、個人の場合は本人や支配人が、不正な行為や不誠実な行為等をするおそれがないと明らかでないといけないとされいます。
※通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。
要件4.請負契約をするのに足る財産的基礎又は信用があること
許可を申請時において建設業を請け負うにたる財産的基礎又は信用を有している必要があります。
具体的には次の要件が必要となります。(一般許可と特定許可では要件が異なります)
※通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。
1)一般許可の場合
下記のいずれかに該当すればOKです。
- 自己資本の額が500万円以上であるこ
- 500万円以上の資金を調達する能力が有すること(預金額が500万円以上あること等)
- 許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること(新規許可では該当せず、5年毎の許可更新に該当)
2)特定許可の場合
下記のすべてに該当しなければいけません。
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
要件5.欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする事業者が建設業法(第8条等)で定められている欠格要件に該当しないことが必要です。
具体的には成年被後見人ではないことや、破産して復権していない者ではないこと、建設業法違反で処分されていないこと等が挙げられますが、通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。
この条件を満たしてれば許可は取れることとなりますが、実際の申請は書面で行われているため、これらの要件を書面で証明を行う必要があります。
その証明がケースバイケースで頭を悩ませる部分となるケースがとても多いのが事実です。実際に代行する行政書士の能力の違いがここで発揮されると言っても過言ではありません。
建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。
当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。